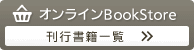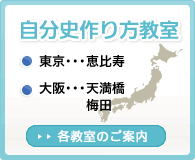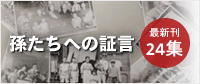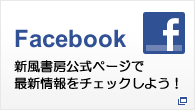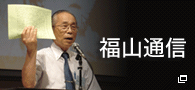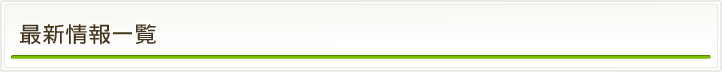ホームページ > 最新情報
身近な小さい生き物たち2
2023年10月25日(水)
主な目次
- 春
- 夏・秋
- 変態
- 恋愛
- 子育て
- 食事
- 擬態
- 住みか
- 死
- 冬
- 春へ
繊維の街、大阪
2022年05月20日(金)
大坂城と大坂・摂河泉地域の歴史
2022年03月30日(水)
目次
- 第1章 「国生み神話」の風景―古代王権となにわ―
- 第2章 四天王寺と熊野―熊野街道が結んだ二つの聖地―
- 第3章 西国巡礼と四天王寺の信仰
- 第4章 戦国時代の摂河泉
- 第5章 大阪府岬町の織豊期
- ◆第一部 古代・中世のなにわと摂河泉
- 第6章 大坂城と城下町大坂―本願寺から大坂城へ―
- 第7章 「豊臣期大坂図屏風」に描かれた船場の景観
- 第8章 秀頼時代の豊臣家―なぜ大坂の陣は起こったのか
- 第9章 徳川大坂城―西国支配の拠点―
- 第10章 大坂城と狐
- ◆第二部 大坂城と城下町大坂
- 第11章 豊臣秀吉――治水とまちづくり
- 第12章 大和川付替えに至る歴史的経緯
- ◆第三部 淀川・大和川の治水
- 第13章 江戸時代の庶民の旅と大坂
- 第14章 住吉大社と平野郷
- 第15章 松原市・屯倉神社伝来の〝おめぶと〟
- ◆第四部 近世の旅・信仰・祭礼
- 第16章 「引札の歴史」概観
- 第17章 人気〝東西屋〟ライバル物語―丹波屋九里丸とさつま屋いも助―
- 第18章 プロレス、日本上陸―明治の異種格闘技戦
- ◆第五部 引札の歴史、引札が語る歴史
著者紹介
北川 央(きたがわ・ひろし)
- 1961年大阪府生まれ。神戸大学大学院文学研究科修了。1987年に大阪城天守閣学芸員となり、主任学芸員・研究主幹などを経て、2014年より館長。この間、東京国立文化財研究所・国際日本文化研究センター・国立歴史民俗博物館・国立民族学博物館・国立劇場・神戸大学・関西大学など、多くの大学・博物館・研究機関で委員・研究員・講師を歴任。現在は九度山・真田ミュージアム名誉館長、国立民族学博物館共同研究員などを兼ねる。織豊期政治史ならびに近世庶民信仰史、大阪地域史専攻。著書に『大坂城 秀吉から現代まで 50の秘話』(新潮社)、『大坂城と大坂の陣―その史実・伝承』『大阪城・大坂の陣・上町台地―北川央対談集―』(いずれも新風書房)、『なにわの事もゆめの又ゆめ―大坂城・豊臣秀吉・大坂の陣・真田幸村―』(関西大学出版部)、『神と旅する太夫さん 国指定重要無形民俗文化財「伊勢大神楽」』『近世金毘羅信仰の展開』『近世の巡礼と大坂の庶民信仰』(いずれも岩田書院)、『大阪城ふしぎ発見ウォーク』(フォーラム・A)、『おおさか図像学 近世の庶民生活』(東方出版、編著)、『大和川付替えと流域環境の変遷』(古今書院、共編著)、『大坂城 絵で見る日本の城づくり』(講談社、監修)ほか多数。
大阪春秋第182号
2021年04月01日(木)
| 古典籍でひもとく浪華おおさか13 『大坂奇珍泊』 10 巻3冊 不識演客編 写 大阪府立中之島図書館大阪資料・古典籍課 |
||||
| 春秋対談 仙海義之 VS 橋爪紳也 モダン宝塚のレガシーを継承するファミリーランド、ガーデンフィールズ、そして文化芸術センターへ | 構成 長山 公一 | |||
| 随 筆 春 秋 |
わが街、千林 | 仲野 徹 | 帝国キネマ100周年 | 太田 文代 |
| (俳句)堀川戎・天満戎 | 三村 純也 | 肥後守の思い出 | 金井 紀子 | |
| 志賀直哉「淋しき生涯」と山口謙四郎 | 杉谷香代子 | (短歌)自粛日々 | 吉原 和子 | |
| * * ビ バ !た か ら づ か * * |
||||
| 総論 宝塚の風土と歴史 | 田辺 眞人 | |||
| モダン宝塚の誕生 ─小林一三の洋風化大作戦 | 仙海 義之 | |||
| 宝塚文化創造館と歌劇 | 岡田 敬二 | |||
| 宝塚はキネマの都だった! 撮影所があったまちに生まれた映画祭 | 益田 裕文 | |||
| 手塚治虫と宝塚 ─ゆかりの地をめぐる─ | 田浦 紀子 | |||
| 宝塚市内の古墳紹介 | 新井場 萌 | |||
| 寺内町小浜の成立とその歴史 | 直宮 憲一 | |||
| 宝塚(山本)園芸とその歴史 ─植木のまち・山本─ | 藤本 清志 | |||
| 宝塚温泉の歴史 | 小早川 優 | |||
| 清荒神清澄寺と鉄斎美術館 ─富岡鉄斎との交友を中心に─ | 馬細里わか奈 | |||
| 建築のテロワール ─「砂防都市」宝塚をめぐって─ | 宮本 佳明 | |||
| 「ウィルキンソン タンサン」と宝塚 ─宝塚で生まれ百三十年─ | 鈴木 博 | |||
| 宝塚美術協会の黎明 | 森田 明子 | |||
| 宝塚まち遊び委員会の活動 ─まちのアイデンティティをひも解いて─ | 平野 弥生 | |||
| 宝塚学検定 ─進化つづける地域検定 | 三戸 俊徳 | |||
| 市民が作る宝塚の本「みんなのたからづかマチ文庫」 | 田野 一哉 | |||
| わ た し と 宝 塚 |
||||
| 小林一三(逸翁)の街づくり | 河内 厚郎 | |||
| 夢をみつけたまち宝塚 | 定藤 博子 | |||
| GUTAIの画家、元永定正の傑作は、宝塚で生まれた | 岩佐倫太郎 | |||
| マチの景色を変えてみる | 奥田 達郎 | |||
| ふるさと西谷の魅力を発信 | 龍見奈津子 | |||
| 宝塚 失われた風景を求めて | 増山 実 | |||
| 付録解説 TIME TABLE TAKARAZUKA HOTEL(筆者蔵) | 解説 鈴木 博 | |||
| 俳句(雲の峰) | ||||
| 連句(大阪連句懇話会) | ||||
| 川柳(番傘川柳本社) | ||||
| おおさか詩苑27 預言者 | 苗村 吉昭 | |||
| なにわの画伯 成瀬國晴氏に聞く36 わが町 宝塚 聞き手 橋爪 節也+古川 武志/長山 公一 |
||||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る⑪ 『会館芸術』の中の近代舞踊史 |
李 賢晙 | |||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る⑫ 大阪朝日会館と信濃橋洋画研究所 |
熊倉 一紗 | |||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る⑬ 戦前・戦中期の関西写壇と朝日会館 |
佐々木悠介 | |||
| チンチン電車の沿線から⑭ 走れ大阪春秋 これからも ~本誌第2期の区切りにあたって~ | 工藤 寛之 | |||
| 2019年度大阪検定客員研究員ゼミ報告(メインテーマ:大阪とスポーツ)④ 実は日本マラソン発祥の地 大阪 ─1909年マラソン大競走─ |
高木 昌之 | |||
| ドクターかおるの考古学ワールド⑭ 考古学の可能性 ─新堂廃寺の創建年代をめぐって─ | 粟田 薫 | |||
| 新出 親友・長沖 一を語る 藤澤桓夫インタビュー(昭和五三年三月)⑥ 聞き手 長沖 渉 + 永岡正己/構成 浦 和男 |
||||
| コラム 素人集団『謎解き 喜連村史』執筆中④ | 白川 俊義 | |||
| 第9回「泉大津市オリアム随筆(エッセイ)賞」発表 【最優秀賞】「どんぐりコロコロ」梅田純子/【優秀賞】「白いタオル」久多里スマ子/【優秀賞】「虹色の座布団」中村実千代 |
||||
| 武藤治太の ふらりひょうたん 第36話 遥かなり鐘紡⑫ | 武藤 治太 | |||
| 『大阪春秋』本号(第182春号)で幕 脳梗塞で発行人の責任果たせず残念 | 福山 琢磨 | |||
| 関西・芸術鑑賞日記 アートいえば交友79 | 松本 茂章 | |||
大阪春秋第181号
2021年02月01日(月)
| 古典籍でひもとく浪華おおさか12 『浪華煎茶大人集』1帖 大里浩庵著 天保6年跋 自筆 大阪府立中之島図書館大阪資料・古典籍課 |
||||
| 春秋対談 大森正樹 VS 橋爪紳也 タイガースブランドをつくったデザイナー 早川源一を野球殿堂入りに |
構成 長山 公一 | |||
| 随 筆 春 秋 |
沖縄から大阪へ 大正区に息づく庶民金融 | 平野(野元)美佐 | きのこ担当学芸員のソーシャルディスタンス | 佐久間大輔 |
| (俳句)星の寿命 | 和田 華凜 | パリオの日の思い出 ─共同体への慈しみと文化─ | 大島 賛都 | |
| (短歌)梅の一輪 | 和中 陽子 | 樽廻船の年中行事 ─新酒番船の熱狂─ | 笠井今日子 | |
| * * 浜 寺 も の が た り海 辺 の モ ダ ン シ テ ィ ふ た た び * * |
||||
| 講 演 阪神間モダニズムと阪堺文化 | 橋爪 紳也 | |||
| 浜寺公園いまむかし | 白神 典之 | |||
| ハマスイ! 浜寺海水浴場と浜寺水練学校の歴史 | 渋谷 一成 | |||
| 浜寺 鉄道が拓いた海浜リゾート | 工藤 寛之 | |||
| 浜寺の住宅地開発と郊外型住宅 | 吉田 高子 | |||
| 浜寺建築案内 | 藏中しのぶ | |||
| 工場夜景のある風景 | 北崎 秀和 | |||
| 浜寺と近代文学 ─晶子と鉄幹、露子と豊子の出会い─ | 高橋 俊郎 | |||
| 浜寺公園の宮武外骨 | 浦 和男 | |||
| 南海高師浜線を歩く 海辺のモダンシティ そのおもかげをたずねて | 馬場 文子 | |||
| 図書館資料に見る浜寺 | 大浦 一郎 | |||
| 付録解説 吉田初三郎画『堺市鳥瞰図』(昭和十年)+星三画『堺市鳥瞰図』(発行年不明) | 解説 浦 和男 | |||
| 俳句(火星) | ||||
| 短歌(日本歌人) | ||||
| 川柳(川柳塔社) | ||||
| おかえりなさい花森さん「花森安治『暮しの手帖』の絵と神戸」展 | 鈴木希実枝 | |||
| 大阪市東成区で見つかった災害の記憶 | 片山 正彦 | |||
| 1970年大阪万博パビリオンの行方「大阪万博ビフォー・アフター展 ~あのパビリオンはいまどこに~」について 橋爪 紳也+小谷 洋介 |
||||
| 翻刻 漫才時代 秋田實(『改造』昭和十一年四月号(春季特大号)第十八巻第四号) | 解説 浦 和男 | |||
| 翻刻 煙草屋の角 秋田實(『大阪パック』臨時増刊 新春特輯皇軍慰問号 昭和十六年一月十五日発行 第三十六巻第二号) | 解説 浦 和男 | |||
| コラム 素人集団『謎解き 喜連村史』執筆中③ | 白川 俊義 | |||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る⑨ 朝日会館のコドモ企画 |
山本 美紀 | |||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る⑩ 朝日会館における能楽民衆化への支援 |
中尾 薫 | |||
| おおさか詩苑26 ロバ | 山村 由紀 | |||
| なにわの画伯 成瀬國晴氏に聞く35 立体とわたし 聞き手 橋爪 節也+古川 武志/長山 公一 |
||||
| チンチン電車の沿線から⑬ 歴史を乗せて、明日へ走れ ~開業120周年記念 ライブラリー電車~ | 工藤 寛之 | |||
| ドクターかおるの考古学ワールド⑬ 3つの遺跡を繋いだ一枚の瓦 ─お亀石古墳の平瓦─ | 粟田 薫 | |||
| 2019年度大阪検定客員研究員ゼミ報告(メインテーマ:大阪とスポーツ)③ データから分析する大阪のラグビー 高校ラグビーを中心として |
萩原 理史 | |||
| 新出 親友・長沖 一を語る 藤澤桓夫インタビュー(昭和五三年三月)⑤ 聞き手 長沖 渉 + 永岡正己/構成 浦 和男 |
||||
| 武藤治太の ふらりひょうたん 第35話 遥かなり鐘紡⑪ | 武藤 治太 | |||
| 関西・芸術鑑賞日記 アートいえば交友78 | 松本 茂章 | |||
大阪春秋第180号
2020年10月01日(木)
| 古典籍でひもとく浪華おおさか11 『順慶町夜店詠 狂歌夜光玉』如棗亭栗洞編 棗由亭負米補 文化12年刊 大阪府立中之島図書館大阪資料・古典籍課 |
||||
| 春秋対談(特別編) 70年大阪万博・みどり館「アストロラマ」と舞踏家・土方巽 髙島屋史料館TOKYO企画展「大阪万博 カレイドスコープ ─アストロラマを覗く─」関連セミナー 森下 隆+本間 友+奥野達郎/聞き手 橋爪紳也 |
||||
| 随 筆 春 秋 |
都市のリスク | 森栗 茂一 | 美術館での関西風作品鑑賞のすすめ | 遊免 寛子 |
| (俳句)穴惑 | 茨木 和生 | 大坂名所歩き旅 ─天王寺七坂を巡る─ | 宮元 正博 | |
| (短歌)午後 | 吉村 彰子 | ボランティアでごみ拾いをする彼らが見つけた宝物 | 遠藤 百笑 | |
| * * メ デ ィ ア と 上 方 の 芸 能 * * |
||||
| 総論 メディアと上方の芸能 ~リアルからヴァーチャルへ~ | 井上 宏 | |||
| 特別寄稿Ⅰ ラジオ放送の誕生と大阪の演芸 ~笑いの平和主義に寄せて~ | 木津川 計 | |||
| 漫才と討死 秋田實 鉛筆片手に、余白を埋めるが戦い | 林 千代 | |||
| 漫才作家と時代の移り変わり | 藤田 曜 | |||
| 島ひろし旧蔵台本にみる 放送メディアと漫才の関係 | 浦 和男 | |||
| オルフェが紡いだ 「リズムの歴史」 ─宝塚歌劇の黒塗りと鴨川清作『ノバ・ボサノバ』─ | 藏中しのぶ | |||
| 米朝と枝雀 ~落語とドラマ よもやま噺~ | 長沖 渉 | |||
| 元朝日記者 北岸佑吉所蔵能楽写真 | 関屋 俊彦 | |||
| 映画と上方の芸能、演芸 ~切っても切れない間柄~ | 武部 好伸 | |||
| 関西講談の新聞連載 ~神戸新聞連載における二代目旭堂南陵~ | 旭堂 南海 | |||
| メディアの寵児 初代桂春團治 ~ラジオ騒動と珍品「ものいふせんべい」~ | 桂 文我 | |||
| 話芸の絶滅危惧種をのこす ─続き読み講談を知っていますか─ | 石津 良宗・史子 | |||
| 日本で唯一の演芸資料館 ワッハ上方 | 道上 正俊 | |||
| 神戸女子大学古典芸能研究センター ~開かれた研究の場をめざして~ | 山﨑 敦子 | |||
| 辻山幸一氏所蔵SPレコードコレクションに聴く上方芸の魅力 辻山 幸一+大山 範子+飯塚恵理人 |
||||
| 特別寄稿Ⅱ SPレコードが芸能に与えた影響 | 飯塚恵理人 | |||
| 翻刻 女の一生「第二回 赤ちゃん命名の巻」作・秋田實(昭和二十七年十月十九日放送) | 解説 浦 和男 | |||
| 付録解説 電気大博覧会会場全景図絵(大正十五年 筆者蔵) | 解説 橋爪 節也 | |||
| 連句(大阪連句懇話会) | ||||
| 川柳(川柳塔社) | ||||
| 第179号「特集:きらめけ! 富田林」補遺 富田林とパーフェクト リバティー教団(略称 PL)~誠の道を育むPL~ |
富尾 武彦 | |||
| 「伝統」と「革新」の融合 新たな百貨店のカタチを心斎橋から発信する 大丸心斎橋店の過去・現在・未来 | 鈴木希実枝 | |||
| 芸能文化はなくならない! 関西ゆかりのメンバーが一夜限りの集結 玉造小劇店緊急プロデュース『亥々会 ~息吹の寿ぎ』 | 以倉 理恵 | |||
| 翻刻 ハナ子の身上相談 秋田實(『婦人公論』昭和九年三月号 第十九巻第三号) | 解説 浦 和男 | |||
| 翻刻 漫才の面白さ 秋田實(『会館芸術』昭和十年八月号 第四巻第八号 第三十八号) | 解説 浦 和男 | |||
| おおさか詩苑25 洗浄2020 | 牧田 久未 | |||
| コラム 素人集団『謎解き 喜連村史』執筆中② | 白川 俊義 | |||
| なにわの画伯 成瀬國晴氏に聞く34 時空の旅 ─そして戦後 聞き手 橋爪 節也+古川 武志/長山 公一 |
||||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る⑧ 戦前・戦中の朝日会館における新劇 |
大森 雅子 | |||
| 大阪発のコンビニエンス・ストア「Kマート」の盛衰③ | 井田 泰人 | |||
| 2019年度大阪検定客員研究員ゼミ報告(メインテーマ:大阪とスポーツ)② 大阪の企業とスポーツ ─大阪人を「野球」好きにした企業と企業家たち─ |
前阪 恵造 | |||
| チンチン電車の沿線から⑫ 波乱のメモリアルイヤー ~コロナ禍の阪堺電車2020年の現場~ | 工藤 寛之 | |||
| ドクターかおるの考古学ワールド⑫ 新堂廃寺の造瓦体制 ─新堂廃寺とオガンジ池瓦窯─ | 粟田 薫 | |||
| 新出 親友・長沖 一を語る 藤澤桓夫インタビュー(昭和五三年三月)④ 聞き手 長沖 渉 + 永岡正己/構成 浦 和男 |
||||
| 武藤治太の ふらりひょうたん 第34話 遥かなり鐘紡⑩ | 武藤 治太 | |||
| 関西・芸術鑑賞日記 アートいえば交友77 | 松本 茂章 | |||
孫たちへの証言第33集
2020年08月01日(土)
| 目次 | 著者 | 住 所 (投稿時) |
年 齢 (投稿時) |
|---|---|---|---|
| 体験編 | |||
| ◆第一部 国内での体験 | |||
| 東洋工業で体験した原爆の日のこと | 縫部 栄子 | 広島市 | 90 |
| 長崎で多くの負傷者に埋まり、直接熱射受けず助かる | 高塚 衛 | 宮崎市 | 90 |
| 出水の海軍航空隊整備兵で「九死に一生」を三度得る | 大久保 覚 | 高知市 | 95 |
| 十四歳で海軍二等兵だった私の戦争 | 大石 容一 | 静岡県藤枝市 | 89 |
| 下着を着ていた女子が男の先生に殴られた恐怖 | 足立 恭子 | 京都府宇治市 | 85 |
| 父出征後の新聞販売店を守った母、片肺に | 中野 二三子 | 大阪市 | 85 |
| 「東洋英和女学院」の英の字が「永」に | 栗原 たつ子 | 静岡県三島市 | 92 |
| 学童集団疎開で、寂しさと、ひもじさ味わう | 石山 皓一郎 | 埼玉県ふじみ野市 | 87 |
| やっぱり「届かなかった〝あの〟場所」 | 中村 宏 | 静岡市 | 87 |
| 東京大空襲、学校の防空壕に入れず、助かる | 清水 忠造 | 福島県いわき市 | 83 |
| あの東京大空襲から家族を守った父の姿 | 桜井 広治 | 千葉県船橋市 | 83 |
| 大阪大空襲後の市内を歩き、自宅で母に会う | 伊藤 裕康 | 大阪府豊中市 | 87 |
| 二上山麓から目にした燃え上がる阿倍野周辺 | 森井 淳吉 | 大阪府太子町 | 90 |
| 神戸空襲、焼け残った家財積み父の郷里へ | 尾崎 惠津子 | 奈良市 | 85 |
| 忘れ得ぬ神戸空襲の「あの日、あの時」 | 吉田 美紗子 | 香川県三豊市 | 91 |
| 今治大空襲、家の前を避難民の行列が続く | 八木 一堯 | 愛媛県今治市 | 87 |
| 富山大空襲、避難した群衆の中に姉見つけ抱き合う | 嶋作 恭子 | 富山市 | 88 |
| 母の涙と無念の心も引き継ぎ頑張る | 手登根 光子 | 沖縄県浦添市 | 82 |
| 実家は寺で軍隊駐留 隊長にのらくろ描いてもらう | 本山 冨美子 | 熊本市 | 86 |
| 忘れ得ぬ昭和二十年前後~私の小さな戦争体験 | 森 髙清 | 熊本県玉名市 | 86 |
| 神社で玉音放送聞くとみな無表情だった | 横山 忠雄 | 宮崎西都市 | 88 |
| 国民学校二年で「教育勅語」はこうして覚えた | 山内 研治 | 大阪府豊中市 | 85 |
| 「ゴマすり」、軍隊式の集団疎開を体験させられる | 安原 照雄 | 千葉県習志野市 | 83 |
| 父が校長で転校、私も転校し集団疎開する | 椿 明子 | 大阪府箕面市 | 85 |
| 戦争で疎開に振り回された私の青春 | 今村 怜子 | 静岡県浜松市 | 87 |
| 集団疎開で福島へ行き、縁故で青森へ | 中村 祐子 | 兵庫県芦屋市 | 84 |
| 「集団疎開」で忍耐力など学ぶ | 河井 善三郎 | 名古屋市 | 86 |
| 学童集団疎開「泣いたらあかん」と言われたのに泣く | 吉田 淑子 | 岡山県津山市 | 87 |
| 豊川海軍工廠で第一次女子挺身隊として働く | 背戸 タツヱ | 奈良県橿原市 | 92 |
| 七十五年前の左膝を取り戻したい | 鈴木 明子 | 栃木県壬生町 | 86 |
| 班長の家族六人が防空壕で焼死される | 松崎 貞憲 | 大阪府羽曳野市 | 91 |
| 憧れの女学校に入るも軍需廠へ動員の日々 | 加藤 美知子 | 愛媛県今治市 | 90 |
| ◆第二部 国外での体験 | |||
| ニューギニアで衛生兵として闘うも無惨 | 政本 道一 | 香川県三豊市 | 100 |
| 私が「大連引揚者」の証明に七十年 | 本田 慶喜 | 茨城県ひたちなか市 | 74 |
| 「軍隊は運隊なり」私の幸運な出会い | 久保 正 | 岡山市 | 96 |
| 三井農林海外要員として入社、現地召集後も麻の畑開墾 | 坂上 多計二 | 鹿児島県姶良市 | 95 |
| 実は情報将校だった「英語教師」 | 廣繁 喜代彦 | 東京都 | 90 |
| ◆第三部 亡き人たちの証し | |||
| 〝走り続けた兄〟二十二年の生涯 | 池田 義 | 岡山県真庭市 | 84 |
| 父は軍医で出征するも戦死、母は戦後滋賀で開院 | 大辻 喬夫 | 滋賀県犬上郡 | 81 |
| 多くの犠牲の上に今日在ることを語り継ぎたい | 岡﨑 節子 | 岡山市市 | 83 |
| 父戦死、母再婚せず私を育ててくれる | 村松 洋一 | 静岡県焼津市 | 77 |
| グラマン機銃掃射、二人の学友の死を語り継ぐ | 久田 政男 | 滋賀県東近江市 | 84 |
| 戦争は人を殺させ、人間の心を踏みにじる | 松原 美省 | 三重県伊賀市 | 89 |
| 父眠る島、徳之島へ慰霊塔建立 | 上枝 志鶴代 | 香川県さぬき市 | 85 |
| ◆第四部 特別編 | |||
| 呉海軍工廠水雷部で回天の部品作る | 緒方 久和子 | 京都市 | 91 |
| 「回天」六基を搭載し出撃した伊三十六潜水艦 | 立花 保夫 | 兵庫県姫路市 | 97 |
| 「軍艦足柄」撃沈されるも、積荷の酒樽で生き延びる | 難波 和夫 | 島根県飯南町 | 100 |
| 死の恐怖をはらむ大音響の正体は何だったのか | 平井 喜郎 | 東京都 | 89 |
| 学校が突然兵舎になり、私たちは勤労奉仕に | 信吉 貴美子 | 高知県佐川町 | 88 |
| 御堂筋が「火の川」になった日のこと | 吉川 久美子 | 大阪市 | 88 |
| ぬぎ捨てたシャツに機銃の穴二つ | 黒瀬 杲 | 大阪市 | 88 |
| 関東軍は我々を見棄て、私は李さんに助けられた | 河嶋 時行 | 大阪市 | 82 |
| ミズーリ号へ激突死した石野兵曹の慰霊祭に参加 | 森 隆澄 | 大阪市 | 92 |
| 伝承編 | |||
| ◆第一部 国内での体験 | |||
| 母子の愛に機銃掃射免れ、命を繋ぐ | 法蔵 美智子 | 奈良県生駒市 | 75 |
| 飢餓と特攻で早逝した五人の従兄を想う | 柴田 敦子 | 兵庫県宝塚市 | 81 |
| 〝戦中生まれ派〟 ──きれいなままの防空頭巾 | 川口 祥子 | 大阪府箕面市 | 75 |
| 敗戦後、熊本を襲撃したグラマン | 大沢 寛行 | 東京都 | 69 |
| 未来に残す戦争の体験談 | 秋山 三千代 | 兵庫県芦屋市 | 86 |
| 父、三度目の「赤紙」で出征するも生還 | 下村 勉 | 大津市 | 80 |
| 〝山奥での戦争〟空から落ちて来た米兵 | 吉田 千喜代 | 熊本県大津町 | 79 |
| 和歌山大空襲、業火が全てを焼き尽くす | 永原 瑞子 | 和歌山市 | 75 |
| 青春を母の看病に捧げた義母、心から平和を願う | 青木 道子 | 山梨県南巨摩郡 | 68 |
| 被弾した足を切断、生きる気力失う | 梅田 秀雄 | さいたま市 | 70 |
| ◆第二部 国外での体験 | |||
| 危機一髪を体験した父のインパール作戦 | 辰巳 政司 | 奈良県大和高田市 | 83 |
| 父はグアム島で戦死、母は無理が祟り肺結核に | 笠井 剛州 | 兵庫県加古郡 | 77 |
| ◆第三部 亡き人たちの証し | |||
| 残された戦記から浮かび上がる祖父の姿 | 福壽 みどり | 鳥取市 | 46 |
| 「靖国神社の父は神様」と教えられ亡き父の夢を見る | 熊代 和子 | 和歌山市 | 90 |
| インパール戦で戦病死した伯父が残した四冊の日記 | 鈴木 和子 | 宇都宮市 | 71 |
| 父からのカタカナ書きの手紙 | 藤原 守幸 | 愛媛県今治市 | 81 |
| 終戦後の事故で亡くした長男想い慰霊碑を建てる | 田村 秀子 | 高知県吾川郡 | 85 |
| 戦後七十余年を過ぎて、亡き父と母を知る | 塚本 眞人 | 静岡県藤枝市 | 74 |
| ◆第四部 戦後、それからの私たち | |||
| 忘れられない写真と二十四の瞳の紙芝居 | 森 崇 | 香川県小豆郡 | 75 |
| 「平和の鐘を鳴らそう」歌詩作り合唱 | 岡部 学 | 岡山県倉敷市 | 76 |
| ◆第五部 特別編 | |||
| 特攻隊の誘導、途中でエンストし命落とす学生や哀れ | 大牧 昭夫 | 栃木県鹿沼市 | 70 |
| 医師として刈り出された父の語る原爆 | 富永 敦子 | 静岡県藤枝市 | 77 |
| 哈爾濱学院25期生、南寮退去前後のことども | 横山 享 | 大阪府羽曳野市 | 76 |
大阪春秋第179号
2020年07月01日(水)
| 古典籍でひもとく浪華おおさか10 『虎狼痢治準』1巻 緒方洪庵訳 安政5年刊 大阪府立中之島図書館大阪資料・古典籍課 |
||||
| 春秋対談 橋本啓子 VS 橋爪紳也 オフィスビルの先駆け 堂島ビルヂング100年のあゆみ |
構成 三木 学 | |||
| 随 筆 春 秋 |
大阪万博のレガシー | 中牧 弘允 | 大阪の竹工芸家 田辺竹雲斎 | 宮川 智美 |
| (俳句)花の下 | 宇多喜代子 | 画家・小野田實の黎明期 | 本丸 生野 | |
| (短歌)泣きそうなシリウス | 佐治 洋子 | 太閤さんで終わらない伏見城 | 若林 正博 | |
| * * き ら め け ! 富 田 林 * * |
||||
| インタビュー 吉村善美 富田林市長に聞く 市制施行七〇周年記念 ありがとう七〇年 これからも富田林 みんなが幸せに暮らせるまちに 聞き手 長山公一+小林義孝 |
||||
| 富田林百万年 ~早送り・つまみ食いガイド | 粟田 昌 | |||
| 富田林寺内町の成立 | 大澤 研 | |||
| ふるさとPR大使 マリアさんとゆく 富田林寺内町散歩 北崎 秀和+湯山クリスタ マリア |
||||
| 大都市・大阪府で唯一の重伝建地区「富田林寺内町」 ~四六〇年の歴史が息づく~ ~ 住民が継承してきた まちなみ、まちづくり~ |
房田 秀之 | |||
| アケボノゾウの歯の化石と足跡化石の発見 ─一〇〇万年前の富田林の自然を復元する─ | 森山 義博 | |||
| 考古学散歩道 富田林の古代遺跡をたずねて | 粟田 薫 | |||
| 牛頭山醫王院龍泉寺の歴史 | 中村 浩(浩道) | |||
| 富田林市の楠公史跡と近代の顕彰 | 尾谷雅比古 | |||
| 近鉄長野線と富田林 ~河陽鉄道、河南鉄道、大阪鉄道~ | 松本 弘 | |||
| 忘れられた巡礼者 ─西国巡礼三十三度行者─ | 小林 義孝 | |||
| 富田林という文学の土壌 ─石上露子と織田作之助、そして浪花千栄子─ | 高橋 俊郎 | |||
| 伝統的工芸品「大阪金剛簾」~竹産業、その伝承と歴史~ | 森口 博正 | |||
| 畦道ばかりの富田林ブランド散歩 | 土井 順司 | |||
| 付録解説 沿線名所御案内 アベノ橋大電車/大沿線御案内 大電車(筆者蔵) | 解説 松本 弘 | |||
| 俳句(河内野) | ||||
| 連句(日本歌人) | ||||
| 川柳(川柳塔社) | ||||
| パネルディスカッション「三好長慶を語る ─四国徳島と関西─」 コーディネーター兼パネリスト 天野忠幸氏(天理大学文学部准教授) パネリスト 飯泉嘉門氏(徳島県知事)+濱田剛史氏(高槻市長)+東坂浩一氏(大東市長) 構成 出水康生+長山公一 |
||||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る⑥ 草創期の朝日会館における映画上映 |
紙屋 牧子 | |||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る⑦ 朝日会館と雑誌『会館芸術』における映画の音楽 |
白井 史人 | |||
| 大阪発のコンビニエンス・ストア「Kマート」の盛衰② | 井田 泰人 | |||
| 2019年度大阪検定客員研究員ゼミ報告(メインテーマ:大阪とスポーツ)① 幕末・明治 なにわの鏡心明智流 |
柴田 洋 | |||
| 新出 親友・長沖 一を語る 藤澤桓夫インタビュー(昭和五三年三月)③ 聞き手 長沖 渉 + 永岡正己/構成 浦 和男 |
||||
| 翻刻 こたつこんと 百貨店漂流記 秋田 實 (『サンデー毎日』昭和一二年二月七日第一増大号) |
解説 浦 和男 | |||
| コラム 素人集団『謎解き 喜連村史』執筆中① | 白川 俊義 | |||
| おおさか詩苑24 21世紀の迷路 | たかとう匡子 | |||
| なにわの画伯 成瀬國晴氏に聞く33 ワッハ上方と千日前 聞き手 橋爪 節也+古川 武志/長山 公一 |
||||
| チンチン電車の沿線から⑪ 官幣大社と紀ノ川の石 ~宮ノ下ものがたり 亘り線撤去に寄せて~ | 工藤 寛之 | |||
| ドクターかおるの考古学ワールド⑪ 瓦研究の新方法 ─動作連鎖の概念で観る─ | 粟田 薫 | |||
| 武藤治太の ふらりひょうたん 第33話 遥かなり鐘紡⑨ | 武藤 治太 | |||
| 関西・芸術鑑賞日記 アートいえば交友76 | 松本 茂章 | |||
大阪春秋第178号
2020年04月10日(金)
| 古典籍でひもとく浪華おおさか9 『竹豊故事』3巻 浪速散人一楽著 宝暦6年序 刊 大阪府立中之島図書館大阪資料・古典籍課 |
||||
| 春秋対談 小谷洋介 VS 橋爪紳也 70年大阪万博の遺産を未来へ EXPO’70 パビリオンの取り組み |
構成 長山 公一 | |||
| 随 筆 春 秋 |
大阪で生まれた女と働き方と | 知念くにこ | (俳句)紅 葉 | 三村 純也 |
| 井蛙「難波海」を夢む | 田野 登 | (短歌)風立ちぬ | 鳥本 純平 | |
| * * 四 條 畷 | サ ン タ ク ロ | ス と 出 会 う ま ち | * * |
||||
| インタビューⅠ 東 修平 四條畷市長に聞く 〝市全体 自然体〟 四條畷らしさを活かしたまちづくりを 聞き手 田中朱夏/構成 長山公一 |
||||
| 総論 「四條畷」のなりたち | 小林 義孝 | |||
| 四條畷合戦と楠木正行 | 生駒 孝臣 | |||
| 正行顕彰と四條畷神社の創建 | 尾谷雅比古 | |||
| 河内湖北東岸の弥生・古墳時代 ─讃良地域を中心として─ | 實盛 良彦 | |||
| 河内馬飼の世界 ─讃良の馬飼い─ | 野島 稔 | |||
| 飯盛城と河内キリシタン ─3年間の発掘調査成果から─ | 村上 始 | |||
| 田原の歴史と民俗 ─河内と大和に属す─ | 太田 理 | |||
| 田原地域の発展 | 笹田 耕司 | |||
| インタビューⅡ 絵本作家 谷口智則さん 四條畷から世界へ 絵本がまちを変えていく 聞き手 古橋佳世+小林義孝+長山公一 |
||||
| 35年ぶりの復刻版・四條畷郷土史カルタ ─カルタが市民のふるさととなる─ | 金堀 則夫 | |||
| 「畷高」のあゆみと人 | 石田 榮市 | |||
| 四條畷学園の世界 | 大北 裕子 | |||
| 二つの校舎 ─四條畷学園と四條畷高校─ | 植松 清志 | |||
| サンタに会いに四條畷に出かけよう | 写真・文 北崎 秀和 | |||
| 新しいまちづくりのキッカケ 〝いつも〟が楽しい四條畷へ | 古橋 佳世 | |||
| 市制施行50周年に向けて | 中村由香里 | |||
| 付録解説 大阪新電車地図(大和屋旅館 昭和3年頃発行) | 解説 浦 和男 | |||
| 俳句(雲の峰) | ||||
| 連句(大阪連句懇話会) | ||||
| 川柳(川柳塔社) | ||||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る④ 戦前の朝日会館における洋楽興行(1926ー1937) |
中村 仁 | |||
| 中之島が文化の中心だった頃 ──朝日会館の軌跡を巡る⑤ 戦中期における朝日会館の洋楽興行(1938ー1945) |
山上 揚平 | |||
| 大阪発のコンビニエンス・ストア「Kマート」の盛衰① | 井田 泰人 | |||
| 「大阪は芸術都市になるか」国際シンポジウム&天王寺舞楽と日独トーク | 吉野 国夫 | |||
| 翻刻 断想 文藝上の極北、或は「文藝的な余りに文藝的な」に就いて 長沖 一(『辻馬車』三巻九号 昭和二年) |
解説 永岡 正己 | |||
| 新出 親友・長沖 一を語る 藤澤桓夫インタビュー(昭和五三年三月)② 聞き手 長沖 渉 + 永岡正己/構成 浦 和男 |
||||
| おおさか詩苑23 二十歳の橋 | 今野 和代 | |||
| なにわの画伯 成瀬國晴氏に聞く32 阪神タイガースを描く 聞き手 橋爪 節也+古川 武志/長山 公一 |
||||
| チンチン電車の沿線から⑩ 夜空に届け 熱意と匠のシンフォニー 〜「阪堺電車177号の追憶」ラジオドラマ化〜 | 工藤 寛之 | |||
| ドクターかおるの考古学ワールド⑩ 大量の瓦を前にして ─新堂廃寺出土瓦─ | 粟田 薫 | |||
| 「大阪心斎橋専門商店案内」付記 | 橋爪 節也 | |||
| 第8回「泉大津市オリアム随筆(エッセイ)賞」発表 【最優秀賞】「幸せの毛布」篠本和男/ 【優秀賞】「終活異変」徳地昭治/【優秀賞】「最後の一着」遠藤和代 |
||||
| 武藤治太の ふらりひょうたん 第32話 遥かなり鐘紡⑧ | 武藤 治太 | |||
| 関西・芸術鑑賞日記 アートいえば交友75 | 松本 茂章 | |||
武藤治太の「思うまゝ」
2020年03月20日(金)